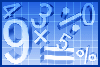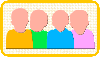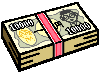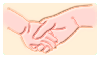全国対応 一生懸命に働くあなたのための |
不当解雇に遭ってお困りのあなた。会社に残業代を請求したいとお考えのあなた。 あなたと同じように会社とのトラブルでお困りの方が、当事務所に労使紛争解決支援プログラム「あっせん・労働審判110番」をご依頼いただき、会社から「解決金」を支払ってもらうことで紛争の解決に至り、本当に良かった、と思っておられます。 この「あっせん・労働審判110番」は、弁護士に依頼するときの半分程度の費用で、弁護士に依頼したときと同等の結果(解決金を会社から得ること)を期待できることがお勧めです。 当事務所では、北は北海道札幌から南は九州鹿児島まで、全国の1都1道2府12県にお住まいの方々から紛争解決支援をご依頼いただき、通算で50件を超える紛争解決のお手伝いをさせていただいております。 とは言っても、本当に紛争の解決を、会社から解決金を支払ってもらう形で解決できるか不安ですよね。 そこで当事務所では、紛争解決に至らなかった場合に着手金を返還する対応策を用意しています。また、着手金をお支払いいただく場合に比べて料金は高くなりますが、着手金無しの料金一括後払い制度も用意しています。詳細はこちらのページをご覧下さい>>あっせん・労働審判110番 不当解雇に遭ってお困りのあなた。会社に残業代を請求したいとお考えのあなた。是非一度当事務所にご相談下さい。 当事務所では、初回無料のメール相談及び電話相談を承っております。この機会に是非ご利用下さい。 |
業務の流れを確認されたい方はこちら >>紛争解決までの流れ
一人で解決できる?労使紛争 不当解雇やサービス残業などの労使紛争を何とか解決したい。でも、弁護士に相談するのは躊躇する。弁護士費 用も高そうだし・・・。できれば自分自身の手で解決したい。そうお考えの方は多いのではないでしょうか。 そもそも、労使紛争をあなた自身の手で、解決を図ろうとした場合、何が障害となるでしょうか。 例えば不当解雇の場合、不当解雇であるという主張の法的な根拠、法的な理論構成が分からない。 次に、どういった方法で、どういった制度や手続を利用すれば上手く解決できるのか分からない。 文書の記述方法が分からない 大きく分けて以上の3点ではないでしょうか。 ということは逆に言えば、上に挙げた3点を上手くクリアできれば、弁護士等専門家の代理人無しでも不当解雇等 労使紛争はあなた自身の手で解決できるのではないでしょうか。 労使紛争を、あなた自身で解決を図る場合、あなた自身でできることとあなた自身では難しくてできないこととを明 確にして、あなた自身ではできないことをどのように処理するかを検討する必要があるでしょう。 法的理論構成 例えば、誰でも料理を作ろうと思えば作れます。でも、美味しいものを食べたいと思えば、専門の料理店に食べに行 くでしょう。専門店の料理人は、料理の作り方は勿論、素材の選び方、器への盛り付け方、料理を出すタイミング、 すべてにおいて研鑽を積んできたものを結実させて、一つの料理としてあなたに提供します。勿論料理を作る道具も 揃っています。だから、あなたが自分で作るよりも速くて美味しい料理を提供できるのです。 不当解雇を法的に理論付けて主張することは、勿論法的に疎い素人でも、書物を紐解いて勉強すれば当然できる ようになります。但し、今すぐにそれができるのか、というと多くの場合はそれは無理ではないでしょうか。 やはりそこは専門家として研鑽を積んだその道のプロに任せる方が賢明です。 法律の専門家としてすぐに思い浮かべるのは、弁護士です。弁護士は厳しい司法試験を合格して司法研修を積ん でいますから、間違いなく法律家でありプロです。 しかし日本国内には数多くの法律があります。弁護士にも得手・不得手というものがあります。全ての弁護士が労 働法に精通しているわけではありません。労働法は労働者保護を目的とした法律群ですから、私法の一般法である 民法の原則をそのままには適用できない場面が多くあります。 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に係る手続きなどを報酬を得て行うことができる唯一の国家資格です。 労働法に精通した「法律家」、というと語弊があるかもしれませんが、労働法の専門家(プロ)であることに間違いは ありません。 特定社会保険労務士は、社会保険労務士の有資格者が更に研修を積み国家試験に合格した者として、労働局の あっせん制度などの裁判外紛争解決制度において、当事者を代理して紛争の解決を図ることができます。 労使紛争を解決させる方法は、直接の交渉、あっせん、労働審判、そして訴訟 不当解雇、サービス残業、賃金の減額、ハラスメントなどの労使紛争を解決させる場合の方法は、会社と労働者と の直接の話し合い(交渉)、裁判外紛争解決制度としての労働局や労政局のあっせん、裁判所の労働審判、そして 最終的な紛争解決制度としての訴訟、このいずれかしか考えられません。労働組合に加入して会社と労働組合と の団体交渉による解決もありますが、団体交渉で紛争が解決しないこともあり、この場合には裁判所の労働審判な どの制度を利用して紛争を解決せざるを得なくなります。 直接の交渉といっても、いろいろなスタイルがあります。テーブルを挟んで話し合うスタイルから、文書のやり取りで 合意を図るスタイル、電話やメールのやり取りといった方法も考えられます。 内容証明郵便文書 労使紛争では、まず最初に労働者から会社に対して要求を行うことが多く、この要求は通常文書に要求項目を記 し、会社に送付することによって行います。通常、この文書には証拠力を付与する目的で内容証明郵便とします。文 書は、法的に見て違法であることを簡潔に記述する必要があります。しかもそれを内容証明郵便文書にする場合に は、内容証明郵便文書の書式に合わせなければなりません。 内容証明郵便文書で何より大切なのは、文書の内容に信憑(しんぴょう)性を持たせることです。信憑性とは、例え ばあなたが高熱でフラフラしているとして、目の前に白衣を着た医者と学生服を着た若者が立っているとします。医 者が「あなたはインフルエンザです」と言い、学生が「単なる風邪です」と言ったとすると、どちらを信じますか。10人 中10人が医者の言った事を信じるでしょう。なぜなら、医者は専門家であり、医者の言ったことは確かで信頼できる からです。信憑性とは、この確かで、信頼できることに他なりません。内容証明郵便文書における信憑性は、専門 家の見解による記述であることが明らかなときに、その度合いが増します。 あっせん あっせんは、裁判外の紛争解決制度として、当事者の調整役であるあっせん委員が、紛争の当事者双方の意見を 調整して双方がお互いに少しずつ主張を譲り合って、和解を図る制度です。労使紛争におけるあっせんは、労働 局、都道府県労政局、弁護士会の紛争解決センター、社会保険労務士会などが設置している民間型ADR機関など がありますが、今日最も利用されているのは、労働局のあっせんでしょう(詳しくはここをクリック >> あっせん)。 労働局のあっせんは、あっせん申請書を労働局に提出することによって手続が開始されます。あっせん申請書は様 式が定められていますが、紛争の経緯や違法性、交渉の経緯や求める解決内容などを詳しく記述したい場合には、 あっせん申請書に別途陳述書や理由書を添付することができます。更にあっせん委員が理解をしやすいように、紛 争に係る証拠資料を添付することもできます。 特定社会保険労務士が、あっせん代理を引き受けている場合、あっせん申請時には必ずあっせん申請書に陳述書 を添付して提出するでしょう。ちなみに当事務所では、陳述書ではなく理由書というタイトルで文書を作成していま す。この理由書は、労働審判手続申立書に準じた書式で作成しています。また理由書には適宜証拠を添付してい ますが、これも労働審判手続申立書の証拠方法に準じて作成しています。これは、あっせんは当事者、特に相手方 である会社に参加を強制できず、また、仮に会社があっせんに参加したとしても期日で合意に至らない場合もあるの で、万が一、あっせんが打ち切られた場合には、即、裁判所の労働審判の本人申立に対応、あるいは弁護士に業 務を引き継ぐ場合に弁護士が労働審判手続に即応しやすいようにとの配慮からです。 ところで、あなたがもし特定社会保険労務士にあっせん代理を委任した場合、あっせん期日にあなたはあっせんに 参加しなくてもよいのでしょうか。法的には特定社会保険労務士が、あっせん手続であなたを、代理、するのですか らあなたがあっせん期日に参加しなくとも問題はありません。しかし、現実には、あなたがあっせん期日にあっせん に参加してあっせん委員に事実について陳述しなければ、望ましい解決を得るのは難しいでしょう。なぜなら、事件 の事実を一番よく知っているのは、代理人ではなく、当事者であるあなた自身だからです。あっせん委員も当事者で あるあなたに直接話しを聞くことによって、紛争の内容をよく理解できるのです。ですから、あっせん期日にはあなた は参加すべきですし、参加しなければなりません。 なお、あっせん期日に相手方である会社の社長や人事担当、代理人等と面と向かって話し合うことはありません。 当事者は交互にあっせん委員と話をします。あなたがあっせん委員と話し合いをしている最中は、相手方は別室で 待機し、逆に相手方があっせん委員と話し合いをしている最中はあなたは別室で待機することになります。 労働審判 労働審判手続は、個人労働者と会社との紛争の解決に特化した審判制度です。審理主体は労働審判委員会で、 労働審判委員会は審判官1名と審判員2名で構成されています。審判官は裁判所の裁判官、審判員は各都道府 県ごとに労働者団体から推薦された者と、会社の経営者団体から推薦された者が各1名ずつです(詳しくはここをク リック >> 労働審判)。 労働審判手続は非訟審理事案ですから、訴訟のように第三者に公開されることはありません。ですから労働審判を 傍聴しようとする場合には、事件の利害関係人が傍聴許可を得た場合にのみ傍聴が許されます。 労働審判手続において大切なことは、労働審判手続申立書を充実させておくことです。証拠も第1回期日までに可 能な限り出し切っておく必要があります。労働審判手続は期日3回以内で原則終了します。第2回目期日までには 調停案が示され、当事者が調停案に応じない場合には、審判が下されることになります。審判の内容は調停案の 内容とほぼ同様のものになると考えておいて間違いありません。ですから審判に異議を申立てる気がないのであれ ば、調停に応じるべきです。 労働審判手続期日は口頭主義が原則です。訴訟の場合のように準備書面などの提出は必要ありません。尤も相 手方の答弁書に対して、補充書面という形で補充的に文書を提出することはあります。ですから、労働審判手続申 立書を上手くまとめることができれば、労働審判手続期日は、極端な言い方をすれば、代理人はあまり仕事があり ません。実際、労働審判手続期日の雰囲気は、会社の会議室での会議のようなものです。労働審判廷はラウンド テーブルといって楕円形のテーブルを囲んで行われます。あなたがイメージしている裁判所の訴訟とは大きく異なる でしょう。審判官も審判員もあなたに対しては難解な法律用語を避け分かりやすい言葉で質問を行い、あなたに対し て意向を尋ねてきます。 仮に弁護士に労働審判手続の代理を委任していたとしても、労働審判手続期日にはあなたも出席する必要があり ます。もちろん、弁護士に代理を委任しているのですから、法的にはあなたが労働審判手続期日に参加する義務は ありません。しかしながら、事件に関する事実については、あなたが一番よく分かっていることであり、あなたから聞 くのが最も審判官や審判員の理解を促すのに役立ちます。つまり審判委員会の心証は、労働審判手続申立書と相 手方の答弁書、そして当事者の言葉によって形成されるのです。実際、労働審判手続期日では、当事者の代理人 である弁護士は、あまり言葉を発する機会はありません。審理の9割以上は審判官や審判員と、当事者であるあな たと、相手方の会社の社長や人事担当などの間でのやり取りで占められます。 ・・・労使紛争をあなた一人で解決できるか? 結論から言うと、それはYES、可能です。ただし、当然のことですが、簡単にという訳にはいきません。 上に述べたように、不当解雇などの労使紛争は、法的な理論構成に基づいて違法性を主張でき、あっせんや労働 審判の手続の方法が理解でき、かつ内容証明郵便やあっせん申請書、労働審判手続申立書を十分作成できれ ば、あっせん期日や労働審判手続期日での、代理人の役目は余りありません。ですから、事件の違法性の主張及 びその主張を根拠付ける具体的事実に関する証拠の準備、内容証明郵便文書の作成、あっせん申請書の作成、 労働審判手続申立書の作成、こういった点について、専門家の助言や指導を適宜得ることができれば、必ずしも弁 護士などに紛争解決を任せる必要はなく、あなた一人でも十分不当解雇を解決できるのではないでしょうか。 社会保険労務士おくむらおふぃすのプレゼンテーション そこで、個別労働関係紛争解決コンサルタント社会保険労務士おくむらおふぃすでは、特定社会保険労務士という 資格を最大限活かして、不当解雇等の労使紛争をあなた一人で解決することを支援することを目的として、次のよう なサービスをご提案いたします。 1 サービスの内容 イ)内容証明郵便文書作成支援 ⇒相手方会社に送付する内容証明郵便文書の素案をご提示いたします。文中には必ず「特定社会保険労務士奥 村隆信の助言の下・・・」という一文を挿入し、文書の信憑性を高めるように致します。内容証明郵便文書の差出に ついてはご依頼人様が自ら郵便局にて行っていただきます。もちろん、手続きの方法については、適宜ご指導いた します。 ロ)労働局あっせん申請書作成及び提出、あっせん支援 ⇒内容証明郵便送付後、相手方である会社からの回答を待って、回答の内容次第では間髪を入れずに労働局にあ っせん申請を行います。労働局のあっせん手続は、まさに特定社会保険労務士の業務の主たる内容です。北は北 海道から南は九州の沖縄まで、日本全国どこの労働局に対しても当事務所からあっせん申請を行います。あっせん 申請書には理由書を添付します。理由書は労働審判手続申立書に準じた書式で作成致します。証拠も調整いたし ます。万が一あっせんが打ち切られた場合で、ご依頼人様が裁判所へ労働審判手続申立を行う場合、この理由書 が役立つはずです。 あっせん期日の調整等は各都道府県の労働局とご依頼人様との間で直接行っていただきます。したがって、あっせ ん手続開始通知や、あっせん期日通知、あっせん打ち切り通知などは、労働局からご依頼人様の元へ送られてき ます。 会社があっせんに参加することとなった場合には、あっせん期日が定められます。そこで、あっせん期日前に一度電 話等にて打合せを行います。労働局での手続やあっせん委員に対する受け答えの仕方など、入念に打合せを行い ます。また、あっせん期日にも、当職が電話口で待機いたします。ご依頼人様があっせん期日の最中に困ったこと が発生した場合、即当事務所へお電話頂ければ、その場にてご助言を差し上げます。 なお、あっせん期日に私の代理をご希望される場合には、交通宿泊費、及び1日当たり5千円の日当を前もってお 支払いいただくことを条件に承ります。 ハ)労働審判手続申立書作成支援 ⇒残念ながらあっせんで紛争が解決できなかった場合、裁判所へ労働審判手続を申立てることをお勧めします。ご 依頼人様が、ご自身で労働審判手続申立を行われる場合には、あっせん申請のときに提出した理由書をご活用く ださい。難なく労働審判手続申立書が出来上がるはずです。もちろん、当職が労働審判手続申立書の作成を支援 いたします。 労働審判手続申立書は、裁判所へ提出しなければなりません。裁判所へはご依頼人様ご自身がご足労頂くことに なります。このとき、帖用印紙や送達用の切手を購入する必要があります。裁判所での手続きの諸々については、 当職が詳しくご説明いたします。 労働審判手続申立書を提出して、補正の必要がなければ、程なく労働審判手続期日呼出状が裁判所から送達さ れてきます。その後第1回労働審判手続期日の1週間くらい前に相手方から答弁書が送られてきます。答弁書の写 しをメールに添付してあるいは郵送で当職にお送りください。第1回期日前に入念な打合せを行います。相手方答弁 書の一文一文を検討して、審判官らとどう受け答えをするか、予習をしましょう。労働審判手続期日には、当職は電 話口で待機いたします。審理の最中にご依頼人様に困ったことが生じた場合には、お電話頂ければ適切にご助言 いたします。裁判所内では緊張されるでしょうから、審判手続開始までにお電話頂ければ、緊張を解きほぐすような ギャグの一つでも・・・。 ニ)労働審判に相手方が異議を申立てた場合 ⇒不当解雇等の労使紛争は、労働審判までにほぼ解決を見るはずです。しかしながら、場合によっては、相手方が 異議を申立てて訴訟へ移行することがあります。訴訟は個人で行うことも当然可能ですが、高度の専門的知識を要 求される場面もあります。ご依頼人様が弁護士に代理を依頼される場合には、業務開始時にお支払いただいた着 手金をお返しいたします。弁護士費用に充当してください。ご依頼人様が一人で訴訟を行われる場合には、最大限 の支援を致します。
不当解雇 解決 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無断転載・複製禁止 社会保険労務士おくむらおふぃす